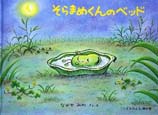長い夏休み、ご家族でどのようにお過ごしになったでしょうか?
1学期の終業式では、夏休みの間に大きなケガや事故にあわないように元気で過ごすための約束をしました。そして、自分の事はできるだけ自分で頑張ってみよう!お手伝いをしよう!という事も話しました。さてさて、どうだったでしょうか?これから子供達に夏の思い出と一緒にこの約束が守れたかどうかを徐々に聞いてみたいと思います。
今年の夏休みには、一年延期された『TOKYO 2020 オリンピック』が開催され、『パラリンピック』は現在開催中です。開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中でいろいろな観点から論じられました。それとは違う次元で、誰もが叶える事の出来ない大きな目標に向かってひたむきに努力してきたアスリート達に目を向けてみると、やはり“感動”と“夢”を与えてもらえた事には間違いないでしょう。
どの競技でも、アスリート達の雄姿には感動させられましたが、その中でも私が一番印象に残って心動かされたのは、スケートボード女子パークに出場した岡本碧優(みすぐ)選手の挑戦でした。決勝で大技に挑戦し、残念ながら転倒してしまいメダルを逃したその戦いには、たくさんのドラマとこれまでの私の中でのオリンピックの見方が少し変わった素敵な瞬間を見る事ができました。メダル獲得に向けて選手達には、私達が想像するに余りある意気込みとこだわりがあるはずです。成功するかしないかギリギリのところで大技に挑んだ岡本選手のチャレンジ精神にも感動しました。そして転倒した後の事、そこには感動と共に爽やかな空気が選手達を包んでいました。悔しさに涙をこらえながら立ち上がりスタートポジションに駆け上がった彼女をたくさんの出場選手達が集まって迎え、笑顔と拍手で抱きかかえてその健闘を讃えていました。そこには、勝負と国境を越えたアスリートの友情が見えました。ライバルである前に同じ夢を追う仲間…技を競い合い磨き合う事でお互いに目標を更新していく者として、大技に挑戦した姿を讃えたのです。そのような姿を見せてくれたのが、10代の若い少女達だった事にも感動しました。これからの時代を背負い動かしていくだろう若者がこんなハートを持ってお互いを尊敬し認め合いながら夢を追っている姿は、まさに※「オリンピック精神」そのもので、このような若者達こそが平和と調和をもって幸せな世界をつくってくれるのではないかと、明るい未来を見たようで頼もしい気持ちになりました。
私達は、つい、国が獲得した金メダル・銀メダル・銅メダルの数を競ってみたり、勝った負けたと一喜一憂したりしますが、オリンピックに全てをかけてきたアスリート達が狙うメダルへの執念とは別に、応援する立場の者としては、そこだけを見るのではなく、果敢に挑む姿や振る舞い等にスポーツマン精神を感じ、世界中の人達に与えてくれる“感動”と“夢”に光を当てて賞賛したいと思うのです。
幼稚園でも、子供達は毎日いろいろな事に挑戦しながら生活しています。その中で、勝ち負けやできるできないだけではなく、友達がどんなに頑張っていたか、努力していたか、どこが素晴らしいかをみつけてあげる事ができる人になって欲しいと思います。大人社会でよく耳にする“結果を出さないと意味がない”“結果が全て”“結果オーライ”と言ってしまえばそれまでですが、子供のうちには、結果は良しと出なくても、それまでの積み重ねや意欲にスポットを当てて、その姿を認め合える仲間作りをしっかり意識させたいと思います。勝者は素晴らしい、敗者はダメ……の意識だと、人の事も自分自身にも肯定感が持てず、喜びが新しい目標をつくり、悔しさはバネにして再挑戦に向かうという次の意欲につながらないと思うのです。前はできなかった事ができるようになった、前よりももっとできるようになった……そんな姿の裏でその子がどんな努力をしていたか、どんな気持ちで頑張っていたかという事を含めて讃え一緒に喜び応援し合えたり励まし合えたりする関係を築いていく事ができる───そして、敵味方、年齢、性別、国、全ての枠を取り除いてリスペクトし合う気持ちを持つ事ができれば、友情や信頼が結ばれ平和へとつながっていくような気がします。他のスケートボードの選手が、インタビューで「ライバルだけど友達だから」という事を言っていました。この言葉に全てが語られていたような気がしました。
同じく、オリンピックに新しく加わったスポーツクライミングでは、競技前に選手達がみんなで、どうやって成功させるかを相談し合っていました。この競技はロッククライミングが始まりらしく、険しい岩山を登るために、クライマーみんなでさまざまな情報を得ながら知恵や技術を出し合い作戦をたてるのだそうです。「力を合わせて」とい“精神”が競技にも持ち込まれているというのです。私には馴染みのない競技でしたが、競技前のその光景にも同じ目標に向かって高みを目指す仲間の気持ち良さを感じました。陸上男子800メートル走準決勝では、国の違うふたりの選手が転倒し手を差し伸べ差し伸べられ、声かけ合ってふたり揃ってゆっくりゴールインしたシーンがありました。感動的でした。そこには、メダルがちらつかないそれ以上の美しいアスリートの姿を見ました。
今回のオリンピックは、新型コロナウイルス感染症により、アスリート達も世の中もなかなか出口の見えない状況の中での開催でした。また、いろいろな立場の方々の意見やご苦労やご苦悩があった事、今もなおその影響を受け大変な思いをされている方がおられる事に目を向けると、感動とは別に複雑な気持ちにもなります。しかし、私は、純粋にこれらのアスリート達によるドラマを子供達もテレビ観戦しているかな?お家の人達と一緒にいろいろな話をしながらどんな事を感じているかなと思いながら見ていました。開催中のパラリンピックでも、個性と力を発揮し活躍するアスリート達の姿に純粋に感動するでしょう。スポーツに限らず子供達の世界でも、いろいろな場面でこれらのドラマと重なる事がたくさんあるはずです。一生懸命頑張る友達を認め、自分もそうありたいと共にチャレンジしみんなで高まり合おうとする気持ち、協力し合いながら一緒に楽しく過ごそうとする精神は、いずれ社会を…世界を突き動かすはず!と思えるのです。
※「オリンピック精神」:スポーツを通して心身を向上させ、さらには文化・国籍など様々な差異を越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合う事で、平和でよりよい世界の実現に貢献する。
2021年9月1日 10:41 AM |
カテゴリー:葉子えんちょうせんせいの部屋 |
投稿者名:ad-mcolumn
梅雨から夏…子供達が水や土や砂と一番仲良くできる季節。雨が降った後は園庭にできた水溜まりに長靴をはいてダイブ。あちらこちらで泥あそび。お日様が出たらプレイTシャツとプレイパンツに着替えて裸足になって水あそび。──子供達の顔は、どの子も笑顔です。子供達のそんな笑顔と歓声がいっぱいの幼稚園は活き活きとしています。
そんな中、朝から賑わう場所があります。小川です。そこには、年長組の子供達を中心にいろいろな学年の子供達が集まって来て様々な声が聞こえて来ます。ブルーギル(いつから、なぜこの小川にいるのかは謎で、本当にこれがブルーギルなのかも定かではありませんが……)を捕まえているのだと言うのです。子供曰く“ブルーギル”は、すばしっこくて、岩と岩の隙間に隠れてなかなか姿を現してくれないので、それを捕まえるのはそう簡単な事ではなさそうです。網を使わず、素手や砂あそび用のスコップやバケツで捕まえようと頑張っていました。『ブルーギル捕獲大作戦』です。私は、その様子を黙って見ていました。先ず岩の隙間をスコップで突きます。隠れているブルーギルを追い出すためです。その時にも、どうやらコツがあるらしく、「水が濁ったら見えなくなるから底にある泥までゴリゴリしたらダメだよ!」と言っている子がいました。なるほど、それにはみんな納得。「じゃあ僕が、バケツで押さえておくから…」と獲物が姿を現すところをすくい捕るというわけです。やっと出てきたら大騒ぎ!ブルーギルの動きに合わせて子供達もあちらこちらに移動していました。すると、他の子が廃材の蛇腹ホースを持って来て「これ!これ!これを小川に沈めて行き止まりをつくろう!」と言いました。せき止めて、ブルーギルの行く手を遮ろうという作戦です。子供達は、そのアイデアに「うん!いいね~!」と、またまた納得。小川に渡してある橋に隠れれば、ホースで大声追い出し作戦!そっちから叫んで!こっちで捕まえるから!」と挟み撃ち────。その現場では、いつの間にか“現場監督”“見はり班”“追い詰め班”“キャッチ班”“せき止め班”と担当が出来ていました。そして、またまた「あっち!あっち!」「そこ!そこ!そこ!」「待って!待って!」「静かにして!」「来た!来た!」と更にエキサイトした声が聞こえて来ました。それからしばらくして、「ゲット~~~!!」という声が聞こえたと思ったら「ヤッタ~~~!!」「スゲー!」「見せて!見せて!」と離れていても、捕獲できた事がわかりました。どれだけ時間がたったでしょうか。随分長い時間頑張っていたような気がします。私も近づいて「先生にも見せて!」と言うと皆が誇らしげに「ほら!」とバケツの中で「参った~」と言わんばかりに身動きできずにいるブルーギルを見せてくれました。「誰が捕まえたの?」と聞くと「ん?俺ら皆で!」と言いました。愚問でした。そうです!それは、みんなの知恵と力で捕まえる事ができたのでした。『ブルーギル捕獲作戦』大成功!でした。「みんな天才だね~、よく捕まえられたね~」と言うと、その一部始終を私に説明してくれました。本当は全部見ていましたが、一生懸命に話してくれる子供達が可愛くて頼もしく思え、私は知らなかった振りをして話し終わるまで聞いていました。そして、「やっぱり天才だ!」ともう一度言うと、子供達は満足そうに顔を見合わせて笑っていました。部屋で飼うとか飼わないとか言っていましたが、子供達はブルーギルが欲しくて捕まえていたのではなく、みんなで捕まえる事が楽しかったのでしょう。結局、小川に逃がしていました。そんな繰り返しを何日もしています。上手く捕まえる事ができる日もあれば、できない日もあり、子供達とブルーギルの根くらべというところでしょうか?捕まえられなくても、それはそれで、”根くらべ”の天才です。

いろいろな廃材を使って、ああでもないこうでもないと作りたい物を自分達の持てる力と技術を駆使して完成させようと頑張ります。完成品を見せて、どうやって作ったかを説明してくれます。周りは切り刻んだ箱や牛乳パック等の廃材でいっぱいの中、やっとできた自信作を持ち上げて「見て!見て!」と自慢します。「○○君は、何でも作れる天才だね。」と言うと、すっかりその気になった顔をします。
縄跳びが……鉄棒が……何回もできるようになったと見せてくれます。「縄跳びの……鉄棒の天才だぁ~」。数回しかできないのに「見て!」と何回も挑戦して見せてくれる子にも「頑張る天才だ!」と認めます。友達に優しくしてあげられる子、「優しい天才!」擦り傷いっぱいつくって遊ぶ子、「わんぱく、やんちゃの天才」なのです。
子供達は、どんな事をどのようにしていても、それがどんな結果であっても、無我夢中でやっている事を認めてもらえれば、自分の力に自信をもつ事ができます。そのどこがあなたの凄い力なのかを気づかせるのです。たとえ失敗に終わったとしてもその過程には、どこか「天才だ」と認めてあげたい事があるはずです。自分の苦手とする事、ダメだと思う事は、長い人生の中でいずれ嫌でも自己分析できるようになります。でも、子供達には早くから苦手意識ダメ意識をもたせるのではなく、僕はできる!私はこんなところが凄い!と思わせてもらえる得意意識があれば、少々の事にはめげない力が備わってくるのではないかと思います。
先週やっと、保育参観で幼稚園でのお子さんの様子を観ていただく事ができました。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、保護者の皆様には幼稚園においでいただく事もままならない状況でした。しかし、この間にでも、子供達はいろいろな事を経験し、順調に幼稚園の生活に慣れ、一人ひとりがちゃんと成長しています。そんな姿をどんな風に観ていただけたでしょうか? その日が、どんな様子であっても、目に見える成長にはもちろんですが、ほんの小さな心の声や成長にも目を向け、お子さんに「あなたは天才!」と言ってくださったでしょうか?そう言ってもらったり、思って見てもらえたりする子供は、その言葉を自分の底力にして成長していくのではないかと思うのです。
さあ!明日から夏休みです。子供達に「あなたは天才だ!」と言ってあげるチャンスがたくさんあるはずです。そんな言葉をたっぷり浴びせてあげてください。
2021年7月19日 10:21 AM |
カテゴリー:葉子えんちょうせんせいの部屋 |
投稿者名:ad-mcolumn
子供達が幼稚園に植えて育てている稲や野菜や花が、順調に生長しています。毎日元気に過ごしている子供達の姿と重なり、幼稚園全体が生き生きとして見えます。先週から、昨年度はできなかったプールあそびも始まり、こうしてゆっくりでも良いからこれまでの日常が取り戻せますように……と願いながら子供達の笑顔を守りたいと思っています。
さて、先月は“母の日”今月は“父の日”と、お母さんやお父さんの事を想う日が続きました。私事ではありますが、この6月は13年前に母が、昨年は父が他界した悲しい出来事があった月です。先日は父の一周忌と母の十三回忌の法要を行い、身内で父と母の思い出話に花が咲きました。私の両親は62年前にふたりで小さな時計店を始め、軌道に乗るまでの数年間は、地元の高校に通う生徒を下宿させたり、母は和裁をしたりして生計を立てていました。私が小学生になって時計店一本になっても両親は、毎日接客や時計の修理等で忙しく働いていました。そんな日々でしたから、全てを親に頼る事も出来ず、色々な事を自分でせざるを得なかったように記憶しています。夕飯時なのに、食卓にはまだ準備ができていなくて仕方なく買い物に行き、できる料理をして妹と弟とで食べる事もよくありました。制服のブラウスのアイロンがけや持って帰るお弁当箱を洗うのは当然自分達の仕事でした。
私が小学校6年生だった夏、市内の小学生の水泳大会に出場する事になりました。(やる気だけで選ばれました。笑)夏休み中、学校へ毎日練習に行きました。その練習を友達のお母さんやお父さんは時々応援に来られていましたが、私の両親は一日も見に来てくれませんでした。忙しい事はわかっていたので仕方がないと諦めていました。そんな中迎えた大会当日、プールの周りにはたくさんのお父さんお母さん達が応援に来ておられました。その中に、なんと、来てくれると思っていなかった母の姿があったのです。ビックリして、母の所に行くと「これ、おやつに食べなさい。頑張りなさいよ。」と言って、小さな紙袋を渡してくれました。中には、プリッツ1箱とチーズが……。大会の事より母に来てもらえた事の方が嬉しくて一日気分が良かったのを覚えています。母は最後まではいませんでしたが、私が大会から帰ると、「50メーターの真ん中あたりで、追い越されたね~。でもよく泳いだね。毎日練習をよく頑張ったよ。それでいいよ。」と凄く凄くほめてくれました。後で聞くと、大会を気にする母に父が「今日はお店はいいから、観に行ってやれ」と言ってくれたらしいのです。
何でもない事のようですが当時の私にとっては、大会の練習の様子を毎日見に来たり聞いてくれたりしていたわけではなくても、私の頑張りの全てを両親はちゃんと分かってくれていた事と、忙しい中、毎日の練習に持たせてくれるお弁当も当日のおやつも最
大の応援の形だった事を感じ、今でも忘れられない思い出となっています。側にずっと居て私の事をしてくれたり気にかけてくれたりする愛情より、はるかに大きな愛情を感じた出来事のひとつになっています。
先日、年中組のある女の子が、登園してすぐに「お腹が痛い」と不調を訴え、職員室で休んでいました。心細くなったのか涙が出て止まらなかったのでお家での様子を聞くためにお母さんに連絡をしました。すると、「確かに、少しお腹が痛いとは言ったのですが、少しすると普段通りに支度を始めたので、体調より気持ちの問題かもしれない。先生、私はいつでも迎えに行きたいんだけれど、今、行ったら気持ちを持ち直せなくならないかな?どうですかね?」と、我が子が弱くなっている気持ちを自ら打破して欲しいという願いと泣いてるのならすぐにでも迎えに行ってやりたいという思いとで迷われていました。結局は女の子の涙は止まらなかったので本調子ではないのだろうという事で迎えに来ていただきました。そのお母さんは、すぐに笑顔で抱きしめ「じゃあ、今日はママと一緒にゆっくりしようか。」と連れて帰られました。甘えから来ているかもしれない弱さを簡単に抱きしめるのではなく「ここを踏ん張ったら…踏ん張らせないと…」と、子供を信じて心を鬼にして支える事も我が子の先を見据えた愛情だと思いました。その女の子は次の日元気にやって来ました。その時お母さんが「先生、昨日は迎えに来させてくださってありがとうございました。」とお礼を言われました。本当は、一刻も早く迎えて抱きしめたかったんだろうと、ここでも見え隠れする親の愛情を感じたのです。
また、少し前に私は、全園児に向けて「4月から少しずつ大きくなっているみんなに頑張って欲しい事があります。自分の荷物(かばんや体操服袋)は自分で持ちましょう。」という話をしました。自分の事は自分で頑張るという生活を小さな事から始め、将来に繋がる責任と自立の気持ちを育てたいと思っているからです。それから子供の中には、「自分で持つ!もうここで大丈夫!」と車から降りて、得意顔で幼稚園の中に入って行く姿を多く見るようになりました。小さな身体には荷物が重そうにも見え、お母さんは子供の背中を心配そうに…でも、笑って見送っておられます。年長組のある女の子がカラー帽子を被らず遊んでいるのを見て、「カラー帽子は?」と声をかけると、「今日忘れたの。私、いつも自分で準備するから、私の失敗!明日は忘れない!」と恥ずかしそうに…でも元気よく笑って答えてくれました。何もかもをお家の人に準備してもらう毎日では、子供は“忘れ物はないかな?全部あるかな?”と自分で気にする事もありません。意識する事が自立に繋がるのだと思います。“自分の事は自分で”──これは、親と子供の間につくる“ほど良い距離”です。付かず離れずの……でも深い愛情のような気がします。
子供達には、お父さんお母さんがこれまで片時も離れず、寄り添い注いでこられた愛情が根っこにあるのですから、どうか、自信をもって、「付かず離れず、見て見ぬふり」をしてみてください。きっとお父さんやお母さんの愛情は伝わります。そして、それを感じながら大きくなろうと力を発揮し始めるのです。実に頼もしいじゃあないですか!子供達が大人になって、その深い愛情にあらためて感謝する時がいつか来るはずです。
2021年6月30日 10:11 AM |
カテゴリー:葉子えんちょうせんせいの部屋 |
投稿者名:ad-mcolumn
新型コロナウイルスの感染拡大が依然として収まらない状況です。わずか数年前なのに、マスクをせず出かけたり人と会ったり集まったりしていた世の中を懐かしく思えたりもします。辛抱辛抱の日々、外出自粛を余儀なくされている今、家庭での過ごし方も以前より変わってきているのではないでしょうか?または、どう過ごせば良いかと悩まれていたりするのでは?
さて、そんな中、1才8カ月になる幼稚園の先生のお子さんと、毎日子守りを任されているおばあちゃんとの微笑ましい話題に触れ癒されました。そのおばあちゃんは、毎日、忙しく帰りが遅くなるお母さんを 孫が良い子で待てるように、いろいろと楽しませてくださっているようです。お母さんである先生は、おばあちゃんが動画に撮ってくださるその様子を時々私に見せてくれます。おばあちゃんと一緒にお墓参りをしたり、自分で一生懸命ご飯を食べたり、庭でおてんばしていたり……。そんな可愛い様子には、それを見るだけでも癒されます。「園長先生!ちょっと見てください。」とその日、見せてくれた動画は、おばあちゃんとその日仕事が休みだったお父さんと三人でホットケーキを作っている様子でした。どうやら絵本『しろくまちゃんのほっとけーき』を読んでもらいながら作っていたようでした。どろどろのホットケーキのタネをおたまで上手にホットプレートの上に乗せていました。2才にもならない子がひとりでするのですからテーブルのあちらこちらも、ぽたぽた どろどろです。「あ~ぁ」と思わず声が出てしまう程でしたが、そのおばあちゃんとお父さんは、それを楽しんでおられるようでした。「○○ちゃん、今、どこ?ぽたあん どろどろ」しばらくすると「ぴちぴちぴち ぷつぷつ」と絵本のシーンを追いながら焼けるのを三人で待っておられました。そして、焼きあがると、その子は満面の笑みで食べていました。
幼稚園でも、その本のホットケーキが焼けるページを読みながら「だんだん焼けて来たね、ちょっと匂ってみる?」と、絵本を子供達の鼻に近づけると「わ~!ほんと!いい匂い!」と言って、ホットケーキが焼けるいい匂いがさもしているかのような反応をします。その時に子供達が思い浮かべている匂いは、これまでに自分が嗅いだ事のある数々の香りの引き出しの中からホットケーキやお菓子の匂いを取り出してイメージしているのです。
年中組の先生がそらまめのさやを持って来て、子供達に剥く体験をさせていました。『そらまめくんのベッド』という絵本を読んで、実際にそらまめを見せてあげようと思ったようでした。「くものようにふわふわでわたのようにあったかい」というフレーズがありますが、そらまめのさやの中を実際に見ていないと、その部分が子供達の頭の中でイメージが湧きにくいのです。剥いてみてふわふわした綿で豆が包まれている事を知ると、まるでベッドのようだ!と感動します。そして、子供達は、そのそらまめに目や口や手足をくっつけてイメージし、そらまめ君達の冒険を一緒に楽しむのです。実際にさやの中のふわふわの綿を見たからこそ、そらまめ君達が眠るベッドが本当に気持ちよさそうだと想像できるのです。
その少し前にはその先生が大きな背の高いたけのこを持って来てくれていました。皮を剥いた後、子供達が「たけのこが百何枚(?)も皮の服を着てたんよ!」と興奮しながら教えてくれました。「このたけのこが大きくなったら何になるか知ってる?」と聞くと「うん!竹!竹の子供だから“たけのこ”なんだよ。」と自信たっぷりに答えてくれました。「そのたけのこ、もしかしたら大きくなってかぐや姫が入る竹だったかもしれないね。」と言うと、昔話がピンとこなかったのか、たけのこと竹とが結びつかなかったのか、キョトンとして残念ながら盛り上がりませんでした。でも、いつかまたその子達が竹を見た時に、何百枚もの皮の服を着たたけのこの事を思い出し、“かぐや姫”の話とその時の感触や匂いや重みを繫ぎ合わせてイメージを膨らませて楽しむ事ができるでしょう。
私が、満3歳児クラスを担任していた10年以上も前の事…。子供達は『おおきなかぶ』の絵本が大好きで、何度も何度も読み聞かせていました。「うんとこしょ どっこいしょ。それでもかぶはぬけません」と繰り返すフレーズがお気に入りのようでした。その頃、我が家の畑にたくさんの大根が育ったので、子供達に大根を抜かせたいと思い、園バスで畑に連れて行った事がありました。小さな子供達が隠れそうなくらいの大きく長い大根の葉を皆でつかんで抜こうとしました。当然の事ながら、ちょっとやそっとでは抜けません。私が、「先生でも抜けなーい!助けて~」と言うと、子供達がどんどん私の後ろに繋がってしぜんに「うんとこしょ どっこいしょ うんとこしょ どっこいしょ!」という掛け声が聞かれ、尻もちつきながら力いっぱい引っこ抜こうと頑張っていました。子供達は、絵本の中のそのシーンを実際に体験した事で、おおきなかぶを抜く時に、どこに力を入れて、どんな風に踏ん張って、どんなに大変な事かがはっきりイメージできて、もっと『おおきなかぶ』の絵本が好きになりました。
 『しろくまちゃんのほっとけーき』
『しろくまちゃんのほっとけーき』
わかやま けん 作
こぐま社
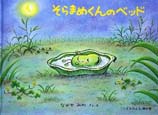 『そらまめくんのベッド』
『そらまめくんのベッド』
なかや みわ 作
福音館書店
 『おおきなかぶ』
『おおきなかぶ』
A・トルストイ 作
福音館書店
絵本を食い入るように見てお話を聞く子供達、そこに出てくる物や景色を実際に見たり触れたりする事で、絵本の世界が実写版になって感じ方に広がりができます。その話の中に自分を登場させて心を躍らせながら、いろいろな人や動植物を自分の身近なものとして慈しみ大切に思う心や、夢を抱く心が育っていくような気がします。
子供達は“空想の世界”と自分が体験した事がある“現実の世界”とをリンクさせて自分なりにイメージを広げ、その絵本の物語に入り込んでいきます。絵本の世界の登場人物と一緒にホットケーキを作っている気分になったり気持ちよさそうなベッドに一緒に入ったりして、しろくまちゃんやそらまめ君達の嬉しかったり楽しかったりする気持ちを想像する事が出来るでしょう。そして、豊かな感性が育っていくのだと思います。人の心や周りの空気を見たり触れたり感じたりしてイメージできる力は、これから先、どんどん世界を広げていく子供達にとって、そこに順応して生きて行く力に結びついていくのではないかと思うのです。
この文章を考えている最中、世界中の子供達に親しまれている絵本『はらぺこあおむし』の絵本作家 エリックカールさんの哀しい知らせが届きました。手掛けられた数々の絵本はこれからも子供達の心の世界を豊かに広げてくれることでしょう。
2021年5月31日 4:46 PM |
カテゴリー:葉子えんちょうせんせいの部屋 |
投稿者名:ad-mcolumn
新しい春の始まり……。春休みには、3月に卒園した1年生がランドセル姿を見せに来てくれたり、中学・高校・大学受験を突破した卒園児達が報告に来てくれたりして様々なスタートを切る子供達の頼もしい姿に元気をもらえたような気がしました。幼稚園でも2021年度がスタートしました。新しい生活に胸を膨らませて元気いっぱいに遊ぶ進級児、初めてお家の人達と離れて過ごす事に不安を隠せない新入園児達。歓喜の声や泣き声、友達や先生を呼び合う大きな声──いろいろな声が幼稚園中に響き渡って賑やかです。
昨年度の終わり、卒園を迎える年長組の子供達に、『おおきくなるっていうことは』(作:中川ひろたか)という絵本を読んであげました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から卒園式の時間短縮、規模縮小等の制限もあり、本来なら卒園式で子供達に伝えたかった事を前もって各保育室を回りこの絵本と共に話をしておきたかったからです。幼稚園を卒園して小学1年生になるという大きな変化は、子供達にとって大きくなる事を実感できる出来事です。それまでの自分と今の自分、そしてこれからの自分のどんな事が違ってきたか?何をもって“大きくなる”というのか?改めて大きくなる自分と向き合って考えて欲しかったからです。『おおきくなるっていうことは…』のフレーズで始まるいろいろな出来事、身体の変化だけではなく心の変化を言葉にして伝えてくれる絵本です。卒園前にその絵本を通していろいろな事を子供達なりに感じて欲しいと思いながら読みました。
大きくなったのは、卒園児だけではありません。進級児達も前よりお兄さんお姉さんになっています。どの子もみんな一つずつ大きくなっています。また、幼稚園に入園したばかりの不安気な新入園児達も、それまでのその子より大きくなっているのです。「大きくなったね」「成長したね」と言うけれど、子供達にとってその言葉はとても嬉しくて誇らしい事なのに、実は抽象的で実感しにくい言葉かもしれません。“大きくなった”“成長した”はそのもの自体が見えないからです。例えば、誕生日を迎え4歳になった。去年まで着ていた服が小さくなって着れなくなった。前はできなかった事ができるようになった。──こうした見える変化を共感してあげる事で子供達は体感しながら(本当だ!私、大きくなってる!)と、大きくなった自分に気づくのです。
満3歳児クラス(さつき組)に入園してきた男の子のお世話を一生懸命にしてくれる年長組(さくら組)のある男の子がいます。名前がたまたま同じなので、先生達が「同じ名前の男の子が今度さつき組に入園して来てくれるからよろしくね。」と頼んだ事がきっかけでした。入園してすぐ手をつないでいろいろな所へ案内してくれたり、一緒に付いて回ってくれたり、あの手この手で泣き止ませたり楽しめたりできるように考えてくれたりもしていました。そのうち、涙が出るそのさつき組の男の子は幼稚園にも慣れてひとりでも楽しく過ごせるようになりました。独り立ち(?)したその子を少し寂しげ(笑)に見守るさくら組の男の子に「○○君がいつも優しく遊んでくれたり、いろいろな所に連れて行ってくれたりしたから、あんなに元気で遊べるようになったんだね。きっとあの子は○○兄ちゃんの事が大好きだと思うよ。ありがとうね。」と言うと、「うん。また、泣いてたら遊んであげる。」と誇らしげでした。大きくなった自分を実感してくれたと思いました。それからも、彼は毎日さつき組の男の子を気にかけてくれています。
さくら組の子供達がトイレに行くと、丁度、大勢の年中組(もも組)の子供達がトイレに居て、順番に出て来るのを並んで通り道を開けてあげていたそうです。さくら組の先生はお兄さんお姉さんらしいその姿が嬉しくて私にも教えてくれました。自分の事より小さい子を優先させてあげようと考えられる──これも大きくなるという事。それがしぜんにできる事も成長したという事。そんな時、「ありがとうね」「嬉しいよ」「助かったよ」というさりげない言葉や態度で返してあげる事は、子供達自身に“(ぼくは)大きくなった”“(私は)成長した”という事を実感させるための“見える化”となります。
今、そんな“大きくなった”子供達の姿をあちらこちらで見かけます。朝、中門でお家の人と離れるのが辛くて泣いている小さな子を見て「連れてってあげようか?」と言ってくれたり、保育室に行って着替えを手伝ってくれたり、泣いている子がいれば先生の所に「あの子が泣いてるよ!」と教えに来てくれたりしています。頼もしいお兄さんお姉さんです。先生達も遠慮なくそのお兄さんお姉さんに頼ります。「これからも、小さなお友達の事をよろしくね」と頼りにする事で“見える化”しているのです。
そして、新しい環境に戸惑っている新入園児達だって、去年までのその子よりぐーんと大きくなっている事を感じてあげてください。中門で大きな声で泣いても、「幼稚園に行きたくない!」と言っても、お昼ごはんがなかなか進まず食べていなくても、みんなと同じ事ができていなくても、それでも、集団生活に一歩踏み入れたその事だけで入園するまでのその子とは違っているのです。「成長する」入り口にいます。大きくなったからこそ!の一歩を踏み出したのです。昨日より今日、今日より明日…とほんの少しでも、変化した様子を認めて喜んであげましょう。子供達のちょっとした日々の成長を…大きくなった事を“見える化”してあげてください。急激に成長を見せてくれる子もいれば、じわじわじっくりタイプの子、3歩進んで2歩さがるタイプの子……といろいろです。お子さんの成長していく様子をお家の人達が余裕をもって見守り、我が子なりのあり様を受け入れる事が大切だと思います。そのたびに、“大きくなった”事を実感させてあげてください。
進級児達も新入児達も、この三次中央幼稚園の環境全てを思いっきり使い、人としてより良く「進化」「深化」して行けるよう、私達も子供達を応援していきます。
今年度も『葉子えんちょうせんせいの部屋』で毎月お付き合いいただきたいと思います。子供達は未来ある宝だと思っています。幼児期の今できる事、今でないとできない事、この時期にこそ必要な事は何か?子供達にとって真の幸せとは何か?を問いながら、保護者の皆様と共に考え合うきっかけとなればと思いながら書かせていただきます。読んでいただく事で子供達の事を更に愛おしく感じてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。
2021年4月28日 4:19 PM |
カテゴリー:葉子えんちょうせんせいの部屋 |
投稿者名:ad-mcolumn
« 古い記事
新しい記事 »